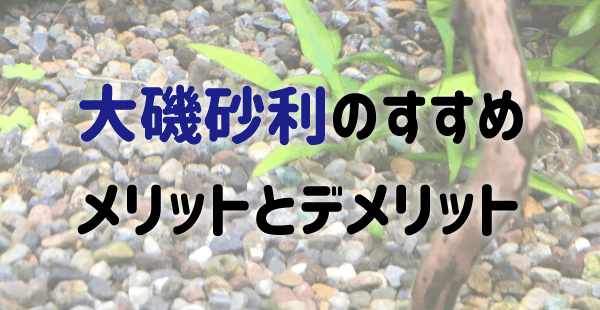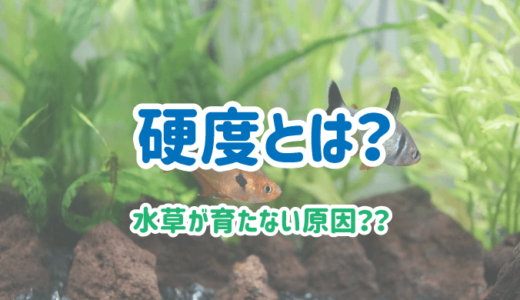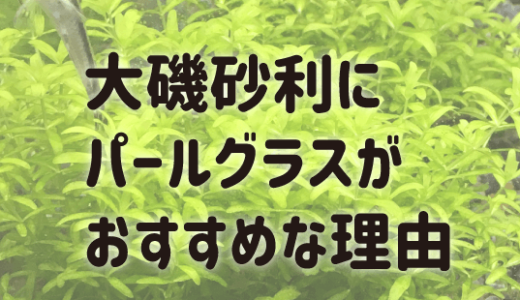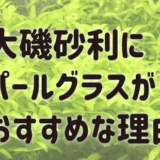アクアリウムにおいてソイルが主流となってきている今ですが、「大磯砂利」の良さを改めて紹介します。
水草水槽では特に「ソイル」が主流となっていると思います。
しかし一般的な水草であれば大磯砂利でも問題なく育てることができます。
むしろ水槽の養分管理は大磯砂利の方がしやすかったりと大磯砂利ならではのメリットも存在します。
大磯砂利のメリット・デメリットを紹介していきます。
読みたいとこから
大磯砂利とは・・?
アクアリウム初心者の方にとっては聞きなれない名前もかもしれませんが、大磯砂利は古くから一般的に使われてきている床材です。
金魚を飼育するときなどによく使われていて、アクアリウムに興味のない人でも一度は見たことがあるかもしれません。

大磯ってなに?
大磯という理由は、昔は神奈川県の大磯海岸で採取した砂だったからだそうです。
現在は大磯海岸での採取が禁止になったため、外国の海岸・砂浜で採取したものがほとんどだそうです。
「磯」という単語だけでは、海や湖の波打ち際という意味もありますね。
大磯砂利のメリット
大磯砂利を使うメリットを紹介します。
半永久的に使える
大磯砂利は石であるので、何度洗っても壊れることがなく、ソイルのように崩れてしまうこともありません。
また、長年同じ大磯砂利を使うことによって、微生物も繁殖し、よりろ過材としてのメリットも高まっていきます。長年愛用している人の中には、大磯砂利に着生している微生物がいなくなるのが怖いので、空気にも触れさせたくないという人もいるくらいです。
使い込んだ大磯砂利はアクアリストの宝ですね。
掃除が簡単
大磯砂利は比重が重いため、プロホースのような道具を使えば、大磯砂利にたまった糞や食べ残しの餌だけを簡単に吸い上げることができます。
生体はもちろんのこと、水草水槽でも糞や餌がたまってしまうと黒ひげコケの原因となったりするため、これらを吸い出せることはとても大きなメリットになります。
ろ過材として優秀
大磯砂利は粒と粒の間に適度な隙間があり、通水性がよいため、微生物の住処として最適で、使い込めば生物ろ過の機能も期待できます。
そのため、ろ過能力の高い底面フィルターとの相性がとてもよく、大磯砂利の水槽では底面フィルターが用いられることも多いです。
魚の色が濃くなる
大磯砂利は黒っぽい色のものが多く、熱帯魚などの色を濃く引き出すことが可能であるといわれています。(熱帯魚や金魚などは回りの色に擬態しようと周りの色が白ければ白っぽく、黒ければ黒っぽく体色を変化させる習性があります。)
硬度(GH)が上がる
メリットでありデメリットでもありますが、石である大磯砂利を入れることにより、水中へカルシウムとマグネシウムが溶け出し、硬度を上げる働きがあります。
硬水を好む魚にとってはメリットで、軟水を好む魚にとってはデメリットですね。
大磯砂利のデメリット
メリットがあればデメリットももちろんあります。ちゃんと頭に入れておきましょう。
アルカリに傾くことがある
大磯砂利は海で採取されるときに多少の貝殻やサンゴが混入しています。飼育水に徐々に貝殻やサンゴが溶け出すことによって水質がアルカリ性に傾いてきます。(phが上昇する。)
一般的な熱帯魚や水草は弱酸性を好むものが多く、デメリットとなってしまいます。
ただし、メダカや金魚などのアルカリの水質を好む生体にとってはメリットとなります。
これについては大磯砂利を酸処理(貝殻やサンゴを取る)することによって回避することも可能です。
酸処理を行わずともアルカリ性に傾かせる原因となる物質は、一年程度ですべて溶けきるといわれており、その後はアルカリ性に傾くことはありません。
養分がない
大磯砂利はただの石なので、水草などが生長に必要とする養分が含まれていません。
そのため、水草を育てる場合には固形肥料や液体肥料を施肥する必要があります。
大磯砂利では水草は育たないとされているところもありますが、肥料さえ与えてあげれば問題なく育てることができます。(僕も大磯砂利で水草を育てています。)
ちなみにこの養分がないということについては、メリットととらえることもできます。もとより不要な養分がないので、自分が施肥した分しか養分が発生せず、養分をコントロールしやすいとも言えます。
ガラスが傷つく可能性がある
大磯砂利は石なので、その他の石と同様にガラスに強く当ててしまうと傷つく可能性があります。
大磯砂利だから特にというわけではありませんが、ソイルと比べると傷つく可能性が高いです。
水草の根張りの良さはソイルに負ける
大磯砂利でも問題なく水草は根を張ってくれ、育てることができますが、水草専用として開発されているソイルには根張りの良さ自体では負けます。
大磯砂利はあくまでも石ですが、ソイルは土を焼結させて作られているため水草にとってはソイルの方が適しているのは間違いありません。
大磯砂利にもサイズがある
大磯砂利にも大粒タイプ、中粒タイプ、小粒タイプといった粒のサイズがあります。
それぞれ特徴が異なるので、適したサイズを選択することが大切です。
大粒タイプ
大粒タイプは粒と粒の隙間が多きすぎるため、水草の根が張れないなど、床材としてはおすすめできません。ただし、その他のサイズや川砂などを床材に用いたレイアウトと合わせると良い雰囲気を演出してくれます。
中粒タイプ
一般的に流通している大きさで、底床としてバランスが良く、生体や水草の種類に関係なく対応できる大きさです。大磯砂利のサイズで迷った場合は、こちらのサイズでよいでしょう。
値段も他のサイズより比較的安く手に入れることが多いようです。
小粒タイプ
細かい大磯砂です。粒と粒の隙間が小さいので通水性が抑えられるためろ過能力は多少劣りますが、水草の根の張りがよく水草水槽におすすめのサイズです。
また、コリドラスなどの低層を生活圏とする生体にも優しいサイズです。
まとめ
大磯砂利につて紹介しました。
大磯砂利が何よりもおすすめというわけではありません。
大磯砂利もソイルも一長一短あり、それぞれの特徴を理解した上で床材を選べるようにこの記事が役立てば幸いです。
大磯砂利を床材とした水草水槽を考えている人はぜひ読んでください。